夏休みの楽しみ方いろいろあります。
落語を通じて、夏休みを楽しむ事が、可能か 新たな自由研究として取り組んだらどうなるかな。
どんな、夏休みになるか、面白いか、つまらないで、飽きるか、実験だ。
イベント通して、小さな計画から始めます。
さあ、夏休み開始だ。
落語を通じた夏休みイベントとどうなるかな。はじめは、大イベント花火を落語で楽しめるか。実験開始。
夏の風物詩「花火」を落語で解説して、花火を、見るだけでなく、それ以外での楽しめるかな?。
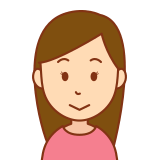
今も昔も有名な、江戸 隅田川花火大会 がある。
歴史は、古く江戸時代には大きなイベントとなっていた。
そもそも隅田川花火大会は、江戸時代に、大飢饉。コレラが流行し、多くの江戸市民が亡くなっ
た。
暴れん坊将軍 徳川吉宗が、死者の慰霊とコレラなどの病気退散を祈願する目的で開始されたようです。
同じ時期に、夏到来の「両国の川開き」兼ねていたようです。
少し前の「コロナ」蔓延、死者多数が発生している。
令和もそのような気持ちで花火を見ることを気持ちを持っていこう。
落語と花火の噺がるかな。実に楽しい噺があります。何回聞いても、面白いです。
「たがや」
あらすじだけで、笑えてしまう。
江戸花火打ち上げの当日にお話しです。
場所は、両国橋の上での出来事です。今と違い、木造ですし、今と比べれば、橋幅もないとことに、江戸中に人が花火見物にきたのですから、大混雑です。
その橋の片方から、馬に乗った武士が共侍を従えて通っている。何が起きてもおかしくない。
その武士の反対側に橋を、大きな道具箱を担いだ「たが屋」も通ってきた。
ちょうど橋に中央でかち合ってしまう。ここからが、見せ場、聴きどころです。
たが屋の道具箱に収めてあった、「巻き竹」がシュッと伸びて、馬上の武士の笠をはじき飛ばした。 これで何もナイ事はない。
武士は、恥をかいたと怒る、お手打ちにすると「ヤリ」突き立ててきた。そこは、江戸職人です。
かわすのもウマい。
武士は、今度は、刀に手をかけて、切ろうとしてきた、その時 職人 たが屋は、一瞬早く、〇〇した。
ここがこの噺のポイントです。
この時に、花火が上りはじめ、「たまや~」「かぎや~」花火屋の屋号とかげ声が上がる。
「たが」とは、風呂桶、たらい、飯台などを縛り、締め付ける竹の道具の事です。
これが語源で「たがを外す」の言葉があります。
緊張など重大な業務を行った後に、緊張などが解けて、ハメを外してしまう事を、昭和までは「たがを外す」と言っていた。令和では使わなくなった言葉かも
その語源が、この落語噺なのかもしれない。
夏休みは、暑い季節です、そこで若者は「キモダメシ」としてお化け屋敷に行きますね、落語にも怖い面白い噺があります。
夏いえば、昔も今の「キモダメシ」して、暑さを一時でも、忘れていたい。特に今の「日本」の夏の暑さには必要です。 もう毎日 暑い熱いかも。
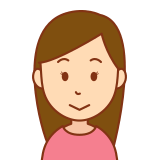
落語にも「キモダメシ」の噺があり、大笑いして暑さを忘れたいです。
「お菊の皿」
この噺の元は、番町皿屋敷 のおどろおどろした怖い恨みの話です。
これを落語噺にした。
ある時から、このお屋敷で身を井戸に投げた「お菊」さんが、毎夜に皿を数える姿が見られるとウワサになる。
そのウワサは、「お菊さんが、皿を6枚数え終わる前に、逃げれば、タタリで死ぬことがないとウワサのなった。
6枚数え終わるまでに帰れば大丈夫と、これまた変な「ウワサ」になった。
そうなると、江戸中に怖いもの見たさの「ヤジウマ」が毎夜に見物にくる。
井戸から現れるが、「丑の刻」と言われいる。今では、夜中 午前1:00以降の時間
お菊さんが、井戸から、現れ、ウラメシイと皿を数え始める。
皿を数えはじめ、見物人は6枚がタイムリミット 3枚目になった、帰ろうとしていますが、お菊さんが、キレイな女性だったから、みんな6枚直前は見物していた。
6枚目になった途端にみんな、逃げ帰る。
ウワサがウワサを呼び、見物客相手に、見物用に「弁当・お酒」販売しだした。
お菊さんにお見上げまで、備えていくようになった。
ここからが、いろいろ噺がある。
①お菊さんが、お見上げが嬉しく、また美味しかったから、食べ過ぎて、太ってしまい、井戸に戻れなくなった。
②ある時「お菊さん」が、皿を9枚、10枚、11枚とどんどん数えれて、18枚になった。
見物客が聞いたら、なんで18枚まで数えたのと聞いたら、お菊さんがなんと「毎日やると疲れてキツイ 明日は休みしようと、今日明日の分を合わせて18枚数えた」と返事した。
ここで、観客は大爆笑です。暑さを忘れしまいます。
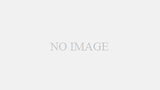
落語に興味が湧いてきましたね。 では、落語を聴きに、寄席に連れて行きましょう。寄席を自由研究しましょう。
落語に興味が湧いたら、一度寄席に行きしょう。
お父さんお母さん
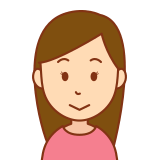
夏休み「自由研究」の題材テーマに子どもと一緒にいきましょう。
寄席は、通常 休みはありません。
ほぼ 毎日 お昼すぎから「昼の部」が開催され、夕方17時位から「夜の部」が開催されます。
親子で行くには、昼ですからいいですよ、それに「寄席」の会場の中で、飲食 お弁当は食べれますから、自宅からお弁当を作って行くのも可能、デパ地下で美味しい贅沢お弁当を持っていくのもいいものです。
寄席にいいとこは、入退場は自由です、いつ入場しても、いつ退場しても自由です。
これだけでも「自由研究」題材になります。他の演芸は、途中入退場は出来ません。
どうして「寄席」入退場自由 飲食(食べ飲み)が自由なのか。その理由、歴史はとかで、十分に研究テーマです。
寄席情報
東京
池袋 駅近い 池袋演芸場 入場料 2800円
新宿 新宿三丁目近い 末廣亭 入場料 3000円
上野 松坂屋近く 鈴本演芸場 入場料 3500円
浅草 雷門見学の後 浅草演芸ホール 入場料 3500円
是非 子どもの為、親の為に寄席に行って、想像の世界をみんなで共有し、大爆笑し、暑さを吹っ飛ばそう!!

コメント