落語家と寄席(新宿末広亭、上野鈴本演芸場)とはどんな関係なのかな。
落語を披露する場所としての寄席演芸場は必要不可欠であるが・・・・・・
初めに「寄席」とはどん場所だろうか、知っているかな。
寄席とは、落語、漫才、講談などの古典芸能を上演する大衆的は演芸場のことです。寄席ときて「よせ」と読みます。
その昔は、「寄せ場」「寄せ席」であったが簡略され「寄席」となったようです。
「落語」は噺家が演じる演芸のことを指し、「寄席」は落語などを上演する場所と理解でいいと思います。
意味合いは、この場所が「人を寄せる」と言う意味があるのである、今風に言えば、コンサート会場かなです。
落語家は、全員が落語の団体に所属している。
落語は伝統芸能であり、基本的には師匠から弟子に芸能を受け継いでいくものである。
その「亭派」を知るのも楽しいですよ(いわゆる ルーツです。)
私の好きな亭は、春風亭 三遊亭 です。
春風亭では、小朝師匠、昇太師匠、
三遊亭では、圓生師匠、円楽師匠(故人)ですが、その芸風は実に楽しい、面白い
みんなもいろいろ寄席で落語を満喫してください。
落語家と寄席の関係はなかなか難しいです。
そもそも寄席と落語家は共存の関係にあり、経済的な面でも寄席運営上においても、お互いを補完しながら反映している。
寄席は席亭側の意見と落語協会側からの希望を打ち合わせをして、まずは「主任」を決める。
この主任が、出演落語家を選定していく。とは言え 主任が若ければ、師匠の出演もそうだが、一門を優先することも
多々ある。
そうすると、人気のない、知られていない落語家だけでは、お客様を呼ぶことができないこともある。
席亭は困ってしまう。
最初にお話したように、経済的な面では落語家も責任があるので、お客さんが喜ぶ、同門落語家も入れなければならない。
このさじ加減が、主任の最大の仕事となる。
ちなみに、新宿末広亭は、昼席で12本 夜席で11本となる。
限られた枠の中を調整し、お客さんを来場させ、師匠および弟弟子などの若い人にもチャンスを上げたいと「主任」は、
頭を悩ませる。
私はこの悩みは、普通の社会、会社でもあることで、その切り盛りも日本社会では必要と思うが、最近は数字が全ての
ようなドライな感じある社会には少し疲れる思いはする。
新宿末広亭と落語家の関係は
8月の主任は、落語芸術協会会長の「春風亭昇太師匠」が実施している。
春風亭昇太師匠は、人気・実力もあり席亭(末広亭の主催者)としては、お客様を呼ぶことができるので、大変満足している。
実際 末広亭に訪問すると会場の1階は満席で、2階の座敷席もほぼ埋まっている状況であった。
落語家は、単独での行動はせずに、どこかの協会に属している。
主に、落語協会、落語芸術協会、立川流、圓楽一門会、上方落語協会 に属している。
今回の「末広亭」の主任は、落語芸術協会 会長である「春風亭昇太師匠」ですから、その出身協会である「落語芸術協会」
出身者が多くを占めることとなる。
ただし、全てを落語にすることはできず、漫才、漫談なども組み入れて、バラエティーに富み、お客様が飽きないようにする
ことも「主任」としての大事な業務のひとつである。
上野鈴本演芸場と落語家の関係は
上野の鈴本演芸場は、落語協会に所属する落語家さんのみしか出演できません。
新宿末広亭とは、ちょっと違った状況のようです。
その理由は、過去にちょっとしたいざこざがあったようです。
それは、桂歌丸師匠にが芸術協会 会長の時に発生した。席亭から落語協会の落語家を今よりも、多く出演させたい
考えを伝えれれた。 それに対し 歌丸会長が憤慨し、芸術協会の落語家を出演させないと言われたされている。
それがまだ、今も継続されている。
私も、以前勤めていた会社で同じようなことがあった。
オーナー社長が何かの商談で取引先 社長と個人的な感情のもつれで、取引停止があった。
一生懸命 会社のために働いている社員には理不尽きまわらない事件であった。
急にそんな過去を思い出した。
落語は古く、伝統にある社会であるから、こじれたら なかなか難しいのであろう。
落語のお噺しにもなりような事である。 なんとなく人間なんだな とつくづく思う。

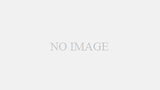
コメント