落語ニュース!蝶花楼桃花さんは、歴史ある名前の「蝶花楼(ちょうかろう)」を名乗る女性落語家です。「桃花(ももか)」という名前もとても可愛らしいですね。現在、落語界で超人気の女性落語家であり、年齢不詳で不思議な魅力を持つ、注目の存在です。
蝶花楼桃花 応援団 落語を楽しもうよ!!
蝶花楼桃花の「蝶花楼」という亭号名跡にはどんな歴史があるのか、また他の亭号名跡にはどんなものがあるのかを調べてみたところ、とても驚きました。
蝶花楼桃花の師匠は「横丁に若様」こと春風亭小朝さんです。
小朝さんは桃花に、どんなことにも挑戦するよう指導していたそうです。
そのため、桃花さんは女性落語家としてさまざまなことに挑戦し、楽しい落語を届けてくれる、目が離せない存在です!
彼女の落語は多彩で、その時々の社会情勢などを巧みに取り入れることで超人気となり、私も大好きな落語家です。
そんな蝶花楼桃花さんは、小朝師匠のもとで修行を積みました。
これからの活躍が本当に楽しみです。
亭号は、落語家の系譜や歴史を知る手がかりとなるものです。
三遊亭には三遊亭の系図があり、円楽師匠の流れなどがあります。
桂には桂の系図があり、歌丸師匠の流れなどがあります。
今回は、女性落語家である蝶花楼桃花さんの「蝶花楼」についてです。
蝶花楼桃花さんのこれからがますます気になります!
蝶花楼桃花さんの面白経歴から、ご紹介からスタートしよう。
蝶蝶花楼桃花さんは若い頃から「生の舞台」が大好きで、宝塚や劇団四季に興味を持っていた。なんと、年齢制限のあるAKB48に24歳で知らん顔して応募し、最終選考まで残ったものの、ついに年齢がバレておじゃんになったというウワサもある。
芸の最高峰である歌舞伎役者を目指したが、歌舞伎は女性が入れない世界のため断念。
そこで出会ったのが「落語」で、これが今の蝶花楼桃花の始まりだった。
桃花は、一人で何人もの役を演じ、高座の座布団一枚の上だけで表現する凄さに感激し、落語の世界に足を踏み入れたという。
古典落語は男社会で作られ、主人公は旦那や侍、親方、相方は女将さんや女中など、基本的に男性目線の噺が中心だが、桃花はこれを女性目線で作り直し演じるというチャレンジをしている。
寄席で桃花の落語を聴けば、その理由がわかるだろう。
蝶花楼桃花さんは、どうして蝶花楼となったのか。その前に「亭号」について、興味深々不思議を調べた!!
蝶花楼桃花の「蝶花楼」という亭号は、落語家の芸名の苗字にあたる部分のことです。
皆さんがよく知っているものとしては、「三遊亭」「桂」「笑福亭」「春風亭」などがあります。
例えば、三遊亭と言えば、五代目や六代目三遊亭円楽、
林家と言えば、歌丸や文枝、たい平、
笑福亭と言えば、鶴瓶や鶴光、
春風亭と言えば、小朝や昇太、
といった名前が思い浮かぶでしょう。
この亭号は、落語の流派を表すもので、弟子が師匠に入門する際に受け継ぎ、流派に所属することになります。
しかし、昇進すると師匠から新たな亭号を授けられることもあります。
こうした不思議な仕組みも、伝統的な落語の世界の一部と理解してください。
この亭号は、歌舞伎における「市川」や「片岡」といった伝統を表すものと同様の意味を持っています。
蝶花楼桃花さんは、どうして蝶花楼となったのか。、興味深々不思議を調べた!!
蝶花楼桃花さんは、春風亭小朝師匠のところに入門しました。入門もまだ、女性が落語家が少ない時代です、その経緯は別に紹介します。
春風亭小朝師匠入門時には、春風亭ぽっぽ と言うかわいい名前をいただきました。
二つ目に昇進時には、春風亭ぴっかり と小朝師匠の思いと洒落っ気があり、みんなから親しまていました。
真打昇進時、小朝師匠から「蝶花楼 の亭号に、女性らしく 華やかな 桃花」をいただき、蝶花楼桃花として、新たな落語家人生を開始しました。
小朝師匠の強い思いが込められた、名前です。
蝶花楼は、江戸時代からある伝統の亭号です。
春風亭小朝さんの師匠の名前が「蝶花楼小照」でありました。
そして、七代目 蝶花楼馬楽さんが落語家として使用していましたが、2019年に亡くなり、この亭号 蝶花楼が途絶えてしまったのです。
小朝師匠は、師匠である「蝶花楼小照」であったことで、この亭号を途絶えてはいけないと、真打昇進時に、春風亭ぴっかり 改め「蝶花楼桃花」となりました。
この名前に「花」使ったのは、小朝師匠の本名は「花岡宏行」であったことから、この花と大吉になる字画となる「桃」を使用し、「桃花」としたと言われています。
なかなか、おしゃれな落語名ですよね。
これについて、ご当人桃花さんは、春風亭ぴっかりがよかったが、小朝師匠からの厚い思いをいただき、伝統ある「蝶花楼」を使用し、より落語家として精進していく覚悟を決めたようです。
蝶花楼桃花さんは、女性落語家としてのちょっと苦労話しがあるようです。、興味深々不思議を調べた!!
落語の世界はやはり男性社会で、男性落語家は約1000人いるのに対し、女性落語家は約50人ほどしかおらず、全体の5%程度という通常の社会では考えられない割合です。
蝶花楼桃花さんが25歳で入門した当時、厳しい師匠がいて、「女は着付けにつくな」「女には落語の稽古はしない」など、女性であることを理由に厳しい言葉を受けることもありました。
また、高座に上がると「女は落語をやるな」「お前を見に来たわけではない」などとお客様に言われることもあり、当時はまだ男性客がほとんどで、女性客が少ない時代でした。
そんな中、蝶花楼桃花さんは「お前を見に来たわけではない」と言われると、「ついでに見に来てくれてありがとうございます」と返し、それがお客様に受けたのです。このようにして成長してきました。
さらに、「顔だけ売れるようにするな」と言われた際には、「え!可愛いって認めてくれたんですね。ありがとうございます」と返すなど、センスのある切り返しで乗り越えてきました。
これが現在の蝶花楼桃花さんを強くたくましくし、さまざまなチャレンジを続ける原動力となっています。
そのチャレンジの代表例を次に紹介します。
蝶花楼桃花さんは、チャレンジ&チャレンジが「スゴイ」です。、興味深々不思議を調べた!!
蝶花楼桃花さんが主導して、女性だけのイベント「桃組」が開催されました。
「桃組」とは、公演主任の提案から生まれた新たな企画で、興行主に「女性だけの公演」を提案し、了承を得て始まった挑戦です。
企画自体は素晴らしいものでしたが、女性落語家や漫才師を集めて興行として成り立たせるには、人数が「ギリギリ」でした。それでも、当時そのパワーは圧倒的でした。
ひとりでも欠ければ成立しなかったこのイベントが「桃組」です。
現在もこの企画は継続されています。機会があればぜひ参加してください。
蝶花楼桃花さんは、ますます活躍するスケジュールをご紹介します。是非公演に参加しにいきましょう。桃花に会いに行こう!!
12月15日(日)
東京 なかのZERO で開催があります。
13:00~
蝶花楼桃花師走の独演会です。
公演鑑賞費用は、3500円です。
日曜のお昼の開演後は、新宿・渋谷・池袋でその余韻を楽しむのも素敵ですね。
時間があれば、女性落語家・蝶花楼桃花を応援しに行きましょう!

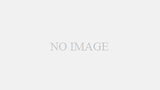
コメント