落語家の「二つ目」とはどんな存在で、どんな仕事をしているのか、実はよく知られていません。
社会に役職や階級があるように、落語の世界にも階級があります。
まず師匠に入門を許されると、落語家の卵である前座となり、師匠の身の回りの世話をしながら修行を始めます。
修行を積み、師匠の許可を得ると寄席などで落語を披露する機会が増え、観客の前に立つようになるのが「二つ目」の段階です。
この段階では落語を演じながら、さらに修行を続けていきます。
「二つ目」とはどんな役回りか!。まずは「前座」!
落語家になるには、好きな落語家に弟子入りして修行を始めます。
最初は前座見習いとして、師匠の身の回りの世話からスタートします。
修行内容は、落語業界のしきたりを学び、師匠の仕事先への同行や荷物持ちをしながら、前座になるための準備を進めていきます。
そして、落語の稽古や着物の着付け・たたみ方、鳴り物の練習などが始まります。
一つ一つ覚えながら進んでいくため、この時期はかなり大変です。
ある程度できるようになると、師匠から許可を得て、ようやく落語家として前座になれます。それだけでも厳しい修行です。
会社員の場合は、新入社員として入社し、会社人や社会人としての常識を叩き込まれる時期にあたります。
この頃は楽しさを感じる余裕もなく、ただひたすら覚えてついていく日々です。この時期に辞めてしまう人も多く、仕事に対する夢や希望と現実のギャップに耐えられないことが理由の一つです。
もう少し我慢すると、本当に仕事ができるようになるのですが。
「二つ目」とはどんな役回り!。ここが大事な時期!
二つ目とは、寄席のプログラムで二番目に高座に上がるところから「二つ目」と呼ばれています。
落語家としてお客様や師匠から厳しく評価され始める時期であり、今後飛躍するための実践と修行の時代です。
着物も紋付、羽織、袴を着ることができるようになり、見た目は一人前の落語家になります。ただし、毎日寄席の高座に上がれるわけではなく、自分で高座や噺をする場所を探さなければならない厳しい時期でもあります。
そのため、噺の稽古をしっかりしないとライバルとの差が広がることになります。この時期をしっかり修行した人は、ついに「真打」として落語家の頂点に立つことができます。
だからこそ、先輩を10人抜きで〇〇が真打となり話題になることもあるのです。
会社でも10年ほど経つと、同期の中でも仕事への取り組み方などで差が出始める時期になります。
平社員から役職者として係長や課長になる人が出てきて、少し差が気になる時期かもしれません。
「二つ目」とはどんな役回!どんな落語家か!
今私が注目している二つ目落語家は「三遊亭美よし」さんです。少し紹介しますので覚えていただけると本人も私もうれしいです。
三遊亭美よしは、富山県出身の女性落語家です。まさに女性落語家の次世代を担う逸材です。落語との出会いは近畿大学4年の時、大阪で寄席を初体験したことでした。楽しくてユニークで面白いと感じ、寄席に通うようになりました。
その中で、落語で使われる言葉の意味に興味が湧き、どんどんのめり込んでいったそうです。一度は大学卒業後にヨガインストラクターをしていましたが、自分の人生に落語が欠かせないと決意し、仕事を辞めて落語家への道を進みました。
落語家になるつてもなかったため、寄席での出待ちという行動力で勝負しました。
当時、語り口などに惹かれていた「三遊亭遊吉師匠」を浅草演芸場で出待ちし、弟子入りを直談判しました。その際、履歴書を作成して手渡し、熱意が伝わったことで面談をしていただき、ようやく弟子入りを許可されました。
得意な噺は滑稽噺で、「時うどん」や「狸賽」などを持ちネタにしています。
笑いを届けられるものの、まだ師や先輩方のように一斉に大爆笑を起こすには至らないのが悩みのようです。ですが、彼女はまだ若く、女性ならではの視点で落語を磨けば、自然と落語ファンがついてくると思います。皆さん、ぜひ期待してください。
他にも前座から二つ目になった落語家がいます。みんなで二つ目落語家を応援しましょう。
特に女性落語家は落語界を変える力を持っていると思います。
皆さんの会社でも、女性の能力の高さや視点、発想の違いに気づいていると思います。
その能力を上司の方々が引き上げ、成功体験をさせてください。きっと成長し、会社の力になるはずです。
二つ目で落語の噺と芸を磨いていきます。
寄席の高座にあがり、実際のお客様との交流することで、マクラの内容と本題の落語噺が、面白くなっていきます。
噺の「間」のポイント、噺のオチに磨きがかかっていきます。
そうすると、寄席に席亭から、他の師匠から、認められるようになっていきます。
ついにその修行の成果として「真打」昇進となっています。
真打となれば、一段と落語好きな方からは、キビシイ視線が向けれてます。
より、笑いを磨いていかなければなりませ。

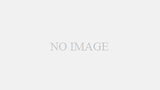
コメント