「蔦重」文化と「落語」文化の繋がりはあったのかな。同じ江戸時代の庶民の文化である。
「蔦重」といえば、蔦屋重三郎を題材にしたドラマであり、実話です。
落語も江戸時代に、芸能として確立し、現代まで続く、芸能であり、日本独特文化です。
今年 江戸時代文化が、今にもいきずいている。
落語、歌舞伎、が江戸の最大の娯楽であった事を知っていますか。
江戸時代には、同じく「落語」庶民の娯楽として開花しようとしていまいた。
「蔦重」と「落語」は、同じ時代に成長していた文化です。
令和の時代にも、繋がっている「江戸芸能」文化、人それが文化です!
「蔦重」について、今 上野美術館で開催中「蔦屋重三郎」コンテンツビジネスの風雲児が開催。蔦重文化は。ビックリです!
江戸の遊郭を中心に、狂歌の隆盛に合わせ、武家、富豪と交流を深め、人気役者、歌舞伎役者、絵師とのネットワークを作り、メディアミックスし、出版業界を作り育成していった人物。
時代が平和な時には、文化が新たな時代へ進む事が可能にまります。
この時代が、江戸文化が隆盛していきます。この後、江戸末期に「戦いの時代」は入る前の心豊かにあっていった時代です。
その書物作りには、購入者である「消費者」目線で、消費者が「なに」に興味をあるのかを調べて、出版物として世間に提供し続けた。
この消費者「目線」は、令和の日本でも同じ事が行われている。消費者が興味を抱いている事とは、「新たな情報」「今より便利な方法」「使いやすい事」が、産業にも影響し、経済の方向迄を決めていく。
皆さんが使用していり「スマホ」が一番理解しやすいです。
スマホは、初めは「電話」機能ですたが、今では、「検索」から「金融」、「交通インフラ」、「見守り」までと、生活に必要なインフラとなっている。
スマホのナイ時代に生活が想像できない位です。
「蔦重」も「消費者」目線での「なに」に興味があるかを、演芸会や、武士、町人から想像して新たな出版物を江戸に提供したのであった。
「蔦重」いた時代に流行した「狂歌」とは、何ぞやです。今は、あまり聞かない言葉。ビックリです!
狂歌とは、どのようなものだったのでしょうか。
江戸時代に江戸庶民に大流行すた「和歌」です。江戸庶民とは、江戸在中の武家から富豪、町民までの、階級に関係なく全て世代です。
特に支配階級である、武士より、江戸町民文化として花開いた。
基本は「5・7・5・7・7」文字言葉の形式に詠まれれる歌です。
和歌は、「雅な風情」を「雅な言葉」で表現する文化人に遊びです。
狂歌は、スタイルは同じですが、「俗な風情」を「雅な言葉や平易な言葉」で詠む歌です。
江戸時代のその時の流行っていた事が題材なることもあり、その時代を表していた。
狂歌の「狂」は「くるう」のではなく、「普通とは違う」というニュアンスがある意味があったと思われいます。
狂歌の狂言は、喜劇につながっていったと言われています。
狂歌は、江戸庶民が楽しんだ娯楽です。
「蔦重」いた時代には、江戸文化として今にもつながる「落語」が娯楽としては花開いた。ビックリです!
「落語」言葉遊びを聞いて遊ぶ文化です。
「蔦重」は、時代の美人画、役者画、物語を江戸の街に本を読む文化を定着させた。
落語といえば、個人、ひとりで、いろんな人物になり、話芸とした伝統芸能です。
道具は、なんと基本 2つだけ 「扇子、手ぬぐい」そして、声 噺です。
さて、始めましょう。
江戸時代には、まだ「落語」と言う名前は、まだ一般的ではなく、「落ち噺(ばなし)」とか、「落ちもの」と言われていた。
特に庶民の娯楽ととして定着したいった。江戸文化となっていった。
怪談噺、風刺噺を題材として、寄席小屋で披露されて、広まっていった。
「蔦重」のいた時代18世紀後半の江戸時代に、寄席芸能として確立されていった。
その立役者として「三笑亭可楽」と言われている。
三笑亭可楽は、本所両国で、落語を披露する場所を確保し、三題や謎解きを行って、お客さんと交流しながら、噺をしていた。
特に「線香」が一分(約3ミリ)灰になるまでの短い時間で噺をを即席で考え、噺をする「一分線香即席噺」を披露した。
特にお客さんから、お題いをいただき、即興で噺をする事で話題を集めた。
話題が呼び、お客さんが、200~300人と人気となった。
このような人気がでると、他の演芸と一緒に実施する「寄席」が生まれるきっかけとなった。
その後に、役者の身の振りなどまねが得意な「初代 三遊亭圓生」が出てきて、評判となり人気者なっていた。
これが、今の「三遊亭」へと繋がっていく。
また、仕掛けや人形を用いて、怪談噺を始めた「怪談の正蔵」と言われた、「初代 林家正蔵」が人気となり、今の「林家」へと繋がっていく。
「蔦重」と「落語」文化は繋がりはあったのか。江戸文化にビックリです!
蔦屋と落語家が直接な繋がりがあったかは確かな資料は残っていません。
ただ、同じ 江戸下町、同じ時代、江戸中期から後期にかなる時代である1770年台以降と重なります。
まったく、繋がりなかったとは思われません。
蔦重は、紙を媒体に、町民庶民に歌舞伎者を浮世絵として世にだし、物語者として、東海道中膝栗毛などを世にだしていました。
落語家は、同じ時代に、庶民に娯楽とし定着していきました。
落語は、書物ではなく、言葉・声でその時代を、世情を風刺したりしていました。
落語は、その後 流派ができ、「三遊亭」「林家」「春風亭」など多くを生み出し、現在にいたっています。

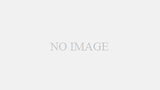
コメント