江戸落語と上方落語は同じ落語だけど、どこが違うのか、不思議に思って調査してみた。
先日(10月末)、大阪の寄席「天満天神繁昌亭」で落語を見てきた。
桂文枝師匠をはじめとする方々の尽力で、大阪に「常設の寄席」が誕生したそうだ。
場所は商店街から少し外れたところにあり、江戸時代の雰囲気が漂う寄席だった。
若い落語家たちが元気よく芸を披露し、修行に励んでいた。
東京の寄席で落語を聴いたことのある私は、大阪の落語が東京のものとは異なることに驚いた。
落語が吉本新喜劇のような雰囲気を持っていると感じたが、これが上方落語の特徴なのだろうか。
また、大阪で「天満天神繁昌亭」に足を運び、新たな落語の魅力を味わいたい。
落語は江戸時代に庶民の娯楽として親しまれ、令和の時代になった今でも変わらず楽しませている。江戸時代から続く娯楽の流れは、特に東京と大阪で広がりを見せている。
東京では「江戸落語」、大阪では「上方落語」として、それぞれ常設の寄席で毎日演じられ、人々を楽しませている。
東西の落語文化を比較してみると、意外な違いや共通点が見えてくる。「江戸落語」と「上方落語」を比べると、驚きや発見があって面白いものだ。
「江戸落語」「上方落語」比較したら、以外な事が、不思議①。
古典落語で有名は「時そば」は、上方落語を、江戸落語の落語家が、江戸風にアレンジした噺です。
今 古典落語では、もっとも知られている落語噺にひとつです。
上方落語では、そばではなく「うどん」が屋台での噺です。
時うどん
上方は、「笑わせること」が優先される文化ある。
時うどんも同じで、店主と客のやりとりは、漫才に「ボケ」「ツッコミ」の形をとっていたようです。
内容も、会計時の勘定をごまかす噺です。
上方落語では、兄貴分がやっていた事を、と弟分が真似て、うまくいかない滑稽噺です。
江戸落語では、うどんが「そば」になっています。
「そば」になった事で、江戸っ子は、素早く、軽く食べる事を「粋」として価値としている。
そばを、すする場面も落語家の腕、芸の見せどころである。
最後、会計する場面が、実にウニーク、店主に勘定を支払う場面、実に面白い。
その状況は、ある職人がそばを食べて、会計時に勘定をごまかすのを、遊び人がのぞき見して、それをマネて、勘定をごかそうとして、多くにお金を払ってしまう。滑稽噺です。
「江戸落語」「上方落語」比較したら、以外な事が、不思議②。
落語の発祥は、上方 京都といわれている。
その後、大阪を中心にした芸能として発展した。上方落語
もう一方は、江戸の娯楽として、発展した江戸落語とわかれて、発展し、今に至る。
1、階級制度
江戸落語には、はっきりした階級制度がる。
入門し、見習い、前座、二つ目、そして真打 となる。(みんなが知っている制度)
上方落語には、明確な階級制度はナイようです。
落語修行歴 5年がひとつに区切り、15年以上が区切りとなる。ゆるやかな制度である。
上方落語は、噺、しゃべりが上手いと、若い時から、いろんな番組にでたりしている。
ちなみに、桂文枝さんは、その昔 桂三枝として、ヤングオーオー、新婚さんいらっしゃい など人気番組に出演していた。
上方の落語家は、個人能力を自由に発揮できるのかもです。
江戸の落語家は、師匠からの修行し、認められるといろんな各方面へ活躍できるのかもです。
東西でやはり、育成の方法も違うようです。
「江戸落語」「上方落語」比較したら、以外な事が、不思議③。
1、道具など
江戸落語は、扇子、手ぬぐい、高座には座布団
上方落語は、扇子、手ぬぐい、見台、小拍子、膝隠し
江戸落語と違う道具「小拍子」は
2本1組の小さな拍子木です。見台に打ち付けて、音を鳴らして、登場人物のセリフ場面や、場面転換など、雰囲気を変えたりする時に使用します。
上方には、よって「見台」も必要になるのです。
この見台の下を隠す役目が、「膝隠し」です。
江戸落語は、自分の声、身振りを使って情景を演じたり、場面変化をだしたりします。
上方落語は、さらに道具を上手く使ってより、明確に、ハデに演出する。
やはり、上方の地域がそうさせるのかもです。
「江戸落語」「上方落語」比較したら、以外な事が、不思議④。
落語を楽しむのに身近かなのは、やはり「寄席」です。
江戸落語は、東京に「常設の寄席」があります。
新宿 末廣亭 その風貌は江戸落語そのものです。
上野 鈴本演芸場 上野公演近くになる地方から来ても直ぐに行ける場所です。
浅草 浅草演芸場 古きよき江戸の街 浅草にあります、浅草観光のひとつです。
上方落語は、大阪に「常設の寄席」があります。
天神橋 天満天神繫昌亭 です。
大阪に下町のアーケード商店街になる寄席です。
商店街で、食べて飲むことも楽しめます。
大阪天満宮にも近いので、参拝できます。

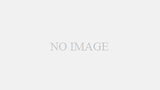
コメント