落語にでてくる噺は、ただ、面白い噺だけでなく、経済についてもしているのです。
昭和に「こんなコマーシャルがありました。
100円でポテトチップは買えますが、ポテトチップで100円は買えません」
ある人は、ポテトチップを200円で買う人がいるかもしれません。
ものの価値はひとによって違います。
落語噺にも、ものの価値(値段)をうまく取り入れた噺で有名なのは、「時そば」です。
そばの値段と代金を払う時のやりとりが、滑稽にはんされます。
新春以降に花見の季節には、また、経済と笑い噺があります。
経済は生き物です。落語も人と人の関りを解りやすくしています。落語噺で経済を学ぼう。
落語にでる花見お酒噺からをご紹介!
落語の「花見酒」という噺があります。江戸の下町長屋に、酒好きで知られる辰さんと熊さんが住んでいました。
桜の季節になり、兄貴分の辰さんが「浅草や向島で桜がきれいに咲いているらしい。あの辺りは茶屋もなく、桜を見て帰るだけだ」と話します。「そこに俺たちが酒を運んで、一杯10銭で売れば大儲け間違いなしだ」と盛り上がり、江戸の知り合いの酒屋から三升の酒をつけで買い、二人で酒樽を天秤棒で担ぎ、浅草・向島へ向かいました。
最初は稼いでたっぷり飲むことを楽しみに運んでいましたが、後ろを担いでいた熊さんが我慢できなくなり、「商売の酒をただで飲むわけにはいかないが、財布の最後の10銭で一杯買わせてほしい」と頼みます。辰さんは「しょうがない」とその10銭で一杯を売り、熊さんは飲み始めました。しばらくして今度は辰さんが「俺も飲みたい」と言い、先ほど熊さんからもらった10銭で一杯買って飲み始めます。すると熊さんもまた「今の10銭で俺も一杯」と続きます。
こうして二人は代金10銭を行き来させながら酒を飲み続け、浅草・向島に着く頃には三升すべて飲み干してしまいました。桜の見物客が「ちょうどいい時に酒を売りに来た!」と喜びましたが、樽にはもう酒がありません。
辰さんが熊さんに「三升売れたのだから、どれくらい儲かった?」と聞くと、熊さんは財布を出して「10銭しかない」と答えます。「三升売ったのに10銭とはおかしい」と考えた末、二人で交互に10銭で買って飲み干したことに気づきます。「あ、そうか。そりゃムダがねえや」と笑い話のオチとなり、観客が大爆笑するという噺です。
これが経済にどう関わるかは、また調べてお話します。
落語花見酒を経済GDPと連動して考えた不思議その①!
落語のお笑い噺は、辰さんと熊さんが、酒を売って儲けようとしたが、途中で熊さんが10銭で一杯、今度は辰さんが10銭で一杯と、カネを双方で繰り返して払いながら、浅草向島に着いた時には酒は空っぽになる。売り上げは10銭だけと不思議は笑い噺です。
これは、経済で見ると、「おカネがクルクルと回っていて、繁栄しているように見えるが、所詮同じところをグルグル回っていだけ」 これは日本国内でおカネがクルクル回っているだけで、外貨のかっとくとか、実質的な富の増大に何も寄与していない。
これが止まると、何も残っていない虚構だったときずく。これはまるで、平成の「バブル」のようで、景気はよく思っていたが、実は同じとこでおカネが循環していただけのことで、それが止まると、何も無いことが解る。考えさせられることです。
落語花見酒を経済GDPと連動して考えた不思議その②!
この落語の噺を、もう一つの考えで見てみると、この辰さん熊さんの仕事を詳細に分析してみた。
二人は自分達で酒を飲みあかして、購入代金である借金を増やした。手元には10銭しかない。しかし、三升の酒の分量、GDP 国内総生産は増えている。
GDPとは、最終消費物の販売価格の合計である。これは生み出された付加価値である。 この落語にあてはめると、サービスの最終消費の総額となるので、辰さん熊さんが飲んでも、花見客が飲んでも同じになる。
あるべき合計金額が、経済成長したことになる
これで、景気がよくなるとと考えて、みんなで借金すればいいのだと考える。ではこの借金はどうするのか。
まるで、日銀と政府が金と国債のやり取りして、景気がいいと言い。資本を身内で回しているだけで、借金を増やしているだけと話す、経済学者もいる。
落語花見酒を経済GDPと連動して考えた不思議その③!
90年代米国経済は、低所得者向けのサブプライムローンを組んだ債務担保証券を世界中にバラマキ、まるで悪酔いさながらに、国際金融危機と世界同時不況を引き起こし、米国政府は金融機関に巨額の救済資金を投じ、経営破錠した自動車メーカーを国有化さざろえなかった。
会社が大きすぎて倒産できなかった。まるで、空っぽになった酒瓶(会社の債務)を政府の資金(税金と国債)で埋めわせるしかないなかったのである。
落語家の噺である「花見酒」を江戸時代からあったのであるから、江戸の庶民はこのバブルを予言していたのかも知れない。
このように経済を落語の中で勉強すると実によく理解できる。 経済学はこのように実践で使えると教育するべきと理解した。
いかかがでしたか、落語を聞きたく、経済を勉強したくなりましたでしょう。
また、新しい発見したら報告します。お待ちしています。

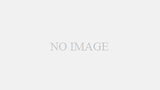
コメント